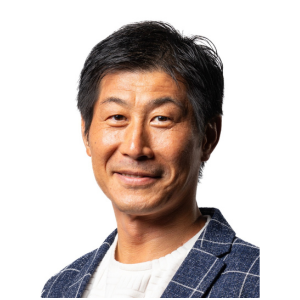暗黙知は足枷か、資産か─生成AIの活用を考察する
私の勤務先ではこの数年来、基幹システムのリプレースに取り組んでいます。ようやく企画フェーズを終え、実行フェーズに移ったところだと言えば、読者の皆様はどう思われるでしょうか。率直に言えば、時間が掛かり過ぎです。ご多分に漏れず、業務要件定義に苦労しています。
だれかが悪いわけではありません。要件定義を担うメンバーはベテランが多く、現在のやり方と自分たちの経験に一定のプライドを持っています。その影響か、総論賛成でも各論でつまずいてしまい、また総論に戻るとその総論もブレることがしばしばです。ベテランといえども業務の全体像を理解しているメンバーはほぼおらず、世の中のベストなやり方を知っているわけでもありません。縦割りの組織構造も相まって、関係部署間の利害調整の堂々巡りが続きます。
なぜ基幹システムのリプレースは進まないのか
「なぜこのやり方なのか」「この例外処理は本当に必要か」──すべては細切れの「暗黙知」の山に埋もれています。ナレッジマネジメントの基礎理論であるSECIモデルで言うと、暗黙知を共有し(Socialization:共同化)、暗黙知を形式知化し(Externalization:表出化)、形式知を組み合わせて(Combination:連結化)、新しくできた形式知を自分自身の暗黙知として再習得する(Internalization:内面化)、この循環がうまく回ってこなかったのです。
メンバー各位にとっては、正直うんざりでしょう。プロジェクトを担うIT統括側も同じ思いです。そんな焦燥の中で、私はこの暗黙知が足枷になる状態は当社の、ひいては日本企業の大きな弱みだと半ば諦めていました。
しかし、生成AIの進化を目の当たりにするにつれて、その考えが変わり始めています。暗黙知の掘り出し方さえ変えれば、足枷になるどころか資産にすらなり得るのではないか──そう思うようになってきています。
なぜ暗黙知が足枷になってきたのか、改めて整理してみましょう。その昔、暗黙知は足枷どころか、むしろ強みでした。日本企業の現場力、属人的なカイゼン、職人技などの口伝の引き継ぎ、これらは長らく価値を生んできたのです。その半面で、それらを形式知化する優先度は次のカイゼンに取り組むことより低く、業務プロセスや設計意図など様々なことがブラックボックス化していったと思います。
それでも暗黙知を持つ担当者が在籍していれば問題は少なかったでしょう。しかし担当者の退職や異動のたびに“要”が抜け落ち、どこかを変えようとすると要の発掘と再解釈に疲弊してしまうようになったのです。そのことがシステム刷新に時間とお金がかかり、その割には代わり映えしないシステムになる要因かと思います。
変わりたくても変われない──私たちの最大のボトルネックは、暗黙知を形式知に変えることの難しさ、そのものだったと言っても過言ではないかと思います。
生成AIで開く、知識流通の新しい回路
生成AIにより、この難しさを大幅に減らせる可能性があります。SECIモデルの各段階(共同化→表出化→連結化→内面化)において、生成AIを能動的プレイヤーとして組み込むのです。
例えば、会議や現場での会話を文章にして、内容を即座に要約し、用語を統一し、作業手順書や業務フロー図のたたき台を作成する。あるいは既存の文書を引き当てて矛盾や重複を洗い出し、次に読むべき情報を提示する。人間は“意味づけ”と“判断”に集中し、AIは“書き起こし”と“つなぎ直し”を担う──そんな仕組みです。
この仕組みが回り出すと、暗黙知に関する私たちの弱みは反転を始めるはずです。日本企業は大量の暗黙知の堆積を現場に持っています。これまでは掘り起こすコストが高すぎました。
しかし、「話せば形になる」仕掛けがあれば、語りは即日でテキストと図に変換され、翌日のレビューに載せることができます。形式知の整備で先行する欧米型に対し、私たちは“現場に堆積した暗黙知×AIによる表出化・連結化”というかけ算で、変化対応の初速を上げることが可能です。要は、暗黙知を恥じるのではなく、暗黙知を流通させる速度で競うことができるのではないかと思うのです。
ただし、この新しい仕組みを始動させるには、前提となる既存文書の整備が不可欠です。ここでも生成AIが役立ちます。ご存じの通り、既存文書を活用可能なものとするためには、文書の構造化、メタデータの付与、バージョン管理などの処理が必要になります。これにあたり生成AIは、文書の構造を解析し、用語の揺れを吸収し、誤記や重複を除去し、検索性を高めるタグ付けや分類を行うことができます。
このような整備はご存じの通り、RAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)の精度向上に欠かせません。きちんと既存文書を整備すれば、生成AIは出典つきで信頼性の高い回答を提示するようになります。つまり暗黙知を形式知にするために既存文書を整備する、それはRAGの精度向上に直結する──まさに一石二鳥です。
既存文書を整備するのに加えて、暗黙知として埋もれた業務知識を新たに文書の形に整理することも必要かもしれません。
ここでも生成AIが役立ちます。例えば生成AIに業務知識を事前学習させ、それを元に担当者にインタビューする方法です。ベテランの判断基準や経験則を生成AIが自然言語で質問しながら引き出し、構造化された知識として蓄積します。また業務記録やPC操作履歴を生成AIが解析するマイニング型の方法も考えられます。実際の業務の流れや例外処理の傾向を抽出・可視化することで、属人化した業務の表出化が進みます。
最近では、両者を統合した事例も登場しているようです。音声インタビューで得られた知識をリアルタイムで構造化し、ログ解析や文書検索の手法を文脈に応じて適切に選択して知識を補完する──こうした手法は、この新しい回路の実現可能性を大きく広げるものと思われます。
「繰り返し」の中に見える可能性
以上はまだ仮説段階ですし、実装するには壁もあるでしょう。それでも筋はかなりよいのではないかと感じています。生成AIの使いどころは、その機能の本質からして暗黙知の定常的な表出化の支援、これが本命だと思います。暗黙知は私たちの弱みではなく、流通設計さえ整えれば分厚い競争資源になります。
求められるのは生成AIをどう使うかという細切れの利用事例ではなく、生成AIを組み込む前提で知識の流通路をどう設計して実装するか、そのような一連の場を作ることだと思います。場をつくり、流れを生み、語りを形にする──その繰り返しの先に、私たちの暗黙知は資産として価値創出に貢献すると考えます。
筆者プロフィール

渡辺 圭悟(わたなべ けいご)
派遣社員として複数社を経験後、2001年にロームに入社。一貫してIT畑を歩み、業務アプリケーション開発&運用、ITインフラ構築&運用とも下流から上流まで経験。2020年に情報システム部長。2025年4月にIT統括本部責任者に就任。日本の半導体産業を支えるべく、企業ITの最終形態を目指して葛藤中。趣味はお酒と音楽鑑賞。